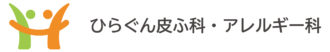アトピー性皮膚炎
Last Updated on 2023年12月29日 by 院長
アトピー性皮膚炎(AD: Atopic dermatitis)は、日本皮膚科学会のガイドラインでは、「増悪・寛解を繰り返す、そう痒のある湿疹を主病変とする疾患であり、患者の多くはアトピー素因を持つ」、と定義されます。アトピー素因とは、①家族歴・既往歴(気管支喘息、アレルギー性鼻炎・結膜炎、アトピー性皮膚炎のうちいずれか、あるいは複数の疾患)、または②IgE抗体を産生し易い素因を指します。
アトピー性皮膚炎の病態で重要なのは、皮膚バリア機能不全と、かゆみ、Th2(最近はタイプ2というそうです)炎症です。
アトピー性皮膚炎の治療は、炎症を抑える(ステロイド外用、タクロリムス外用)、皮膚バリア機能の回復(保湿剤、スキンケア)、悪化因子の除去(環境アレルゲン、食物アレルゲン、金属アレルギーなど)の3本柱です。そのうちのどれもおろそかにはできません。
ステロイドの塗り方も重要で、短い時間に一気に寛解状態にもっていくことが重要です。そして良くなったら一旦やめて、また悪くなったら塗って、というリアクティブな外用方法では、状態を維持できないばかりではなく、病勢が徐々に悪くなってくる可能性があります。寛解に到達してからが、ある意味治療のスタートになります。そこからは、寛解状態を維持するために予防的な外用(プロアクティブ療法)を行って、徐々に外用の間隔を開けていき、週末だけステロイドを塗ったら良い状態が保てる、というあたりをゴールにします。そこまで到達するのには1年〜1年半かかると言われています。
上記のような外用で上手くいく患者さんもいますし、それだけでは不十分な患者さんもいます。ナローバンドUVBなどの紫外線治療も有効です。
最近、Th2(タイプ2)炎症の主たるサイトカインである、IL(インターロイキン)-4の受容体のα鎖のモノクローナル抗体である、デュピルマブ(デュピクセント®)という薬剤が中等症以上のアトピー性皮膚炎に対して用いられ、優れた効果を示しています。ただし、現在のところ投与するためにはいくつかの条件を満たす必要があります。詳しくはこちら。
そして、2020年6月24日に、アトピー性皮膚炎に対する新しい外用薬が20年ぶりに発売されました。外用ヤヌスキナーゼ阻害剤のコレクチム®軟膏です。詳しくはこちら。